
あの登場の演出は、今なお印象深い。
2013(平25)年。年も押し迫ったアソシのサイトのトップページでは、何かをデビューさせる、予告がされていた。
B4は、4.1 4.2と10年以上引っ張ってきたから、そろそろ「5」かな。あるいは、「4.3」のどっちだろと、考えていました。
そして、その年の12/30日(の気がする)に、「B5」シリーズ発表!
しかも、それまでの流れをくむリアモーターの「B5」と、当時から主流で、アソシだけ出していなかったミッド車を「B5M」として発売する2本立て!
でも、年が明けて発売までが長かったですね。
アソシエイテッドRC10 B5M
2014(平26)年 2月 B5から、輸入発売
でも、衝動的に手を出さず(笑)。
時は、各メーカーがミッド車を作り、もてはやされる全盛時代。妥協をしてB5を買うケースもある中で、ここはB5M待ちを選びはしましたが、長く感じました。
B5発売から、日がたつにつれて、まだなのかと待ちわびつつ、B5にするかという妥協と、果ては何も買わない、あきらめムードも漂いました。
いや~1か月近くは、長かったですよ(笑)


しかし、時は来たのです!
2014(平26)年 3月 B5M 輸入発売
ほぼ間を置かずして、購入。
待ったかいがありました。
手に入れてからは、すぐに作り始めました。
B4シリーズから、頑丈さを感じさせる構造と、ゆるみや抜けによるパーツの脱落対策に、格段の進歩を感じながら作りました。
しかし、海の向こうだからなのか、落丁で白紙ページがあり、そこは、ダウンロードして印刷しました。
それ以外は、組み立て時の障害はほとんどなく、極端に言うと、快適に作れました。
何と言っても、18B2T2以降のアソシ車には、それまでのインチねじから、日本で一般的なミリねじに変わったことが大きいです。

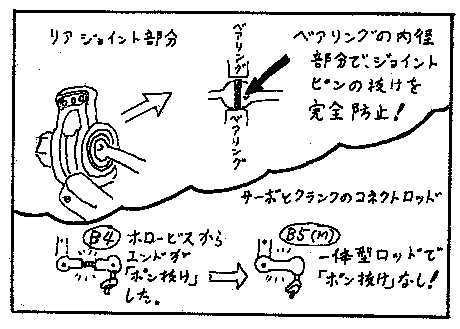
やはり、進化したのは、抜けや脱落対策です。
B4での、ステアリングロッドに使うホロービスが、走行中にゆるみもせずに抜ける「ポン抜け」を解消するべく、樹脂一体成型での対策は、的を射ています。
感心させられたのは、ユニバーサルジョイントのピンが抜けることによる、ドライブシャフトとハブの分離をシャットアウトしたこと。
ピンの両端を、ベアリングの内径部で抑えることで、完全防止する構造は、メンテナンス面での安心感を引き上げます。画期的ですね。
完成させてからは、もちろん走らせます。
その走りは、組み立てたそのままでも、よく走りました。
セッティングとか、したいのですが、走らせる機会がこなくて、手をこまねいているうちに、B6シリーズが登場し、B5Mは、型落ちに。
走らせる回数を増やして、これからも、長く付き合いたい1台ですが、走らせる機会がないと感じて、手放しました。


